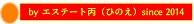生前贈与・土地・評価額:損しないための土地評価と贈与の基本ガイド
親から土地を引き継ぐなら「生前贈与」を考える方も多いでしょう。しかし、土地の評価額を知らずに進めると、
予想外の税金や手続きに苦しむことも。この記事では、生前贈与・土地・評価額をテーマに、贈与税の計算方法や
評価額の調べ方、名義変更の注意点などを解説します。

| ・生前贈与・土地・評価額:なぜ土地評価が重要なのか? ・評価額 調べ方 ・土地 贈与税がかからないケース ・生前贈与・土地・評価額:贈与税・名義変更・手続きの流れ ・生前贈与 土地 名義変更の流れ ・贈与税計算シミュレーション ・生前贈与・土地・評価額:相続との比較と節税の知恵 ・生前贈与と相続どちらが得? ・不動産 3000万円控除と併用できる? ・土地はいくらまで贈与できる? ・関連記事リンク ・生前贈与・土地・評価額:まとめとアドバイス |
生前贈与・土地・評価額:なぜ土地評価が重要なのか?
土地を贈与する際には、その「評価額」に応じて贈与税が決まります。高額な土地を無計画に贈与すれば、多額の
税負担を背負うリスクがあるため、まずは評価額の確認が最初のステップです。
評価額 調べ方
評価額には主に3種類あります。
-
固定資産税評価額:市町村から送られてくる課税明細書に記載されている額。贈与税や登録免許税の算定に使われることが多い。
-
相続税評価額(路線価):国税庁の路線価図で確認可能。市街地ではこの評価額が基準になります。
-
時価(実勢価格):実際に売買されるであろう金額。売却時の譲渡所得の計算などで使われます。
【外部リンク】
-
国税庁|路線価図:https://www.rosenka.nta.go.jp
土地 贈与税がかからないケース
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。また以下のような特例制度もあります:
-
相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税。ただし選択後は贈与者が死亡するまで適用され続けます。
-
住宅取得等資金の非課税制度:一定の要件を満たせば最大1,000万円(省エネ住宅であれば1,500万円)ま
で非課税。
生前贈与・土地・評価額:贈与税・名義変更・手続きの流れ
生前贈与 土地 名義変更の流れ
-
贈与契約書の作成(必ず書面化)
-
贈与税申告と納付(基礎控除を超える場合)
-
登録免許税の納付(固定資産税評価額の2%)
-
司法書士による名義変更登記

名義変更には贈与者・受贈者の印鑑証明書、登記識別情報、住民票、固定資産評価証明書などが必要になります。
贈与税計算シミュレーション
例:固定資産税評価額が1,500万円の土地を子へ贈与した場合
-
課税価格:1,500万円 − 110万円(基礎控除)=1,390万円
-
税率:40%
-
控除額:190万円
-
贈与税額:1,390万 × 40% − 190万円=366万円
かなりの負担になるため、相続との比較や特例制度の活用が欠かせません。
生前贈与・土地・評価額:相続との比較と節税の知恵
生前贈与と相続どちらが得?
生前贈与のメリット
-
資産の早期移転で将来の相続トラブル回避
-
認知症対策(意思表示できるうちに)
相続のメリット
-
小規模宅地の特例や配偶者控除が使える
-
相続税には取得費加算制度あり
特に土地のように高額になりやすい資産は、相続による評価減や控除を使った方が得になる場合が多いです。
不動産 3000万円控除と併用できる?
「空き家の譲渡特例」により、相続で取得した空き家を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から3,000万円が控
除されますが、生前贈与の場合には適用されません。
土地はいくらまで贈与できる?
-
年間110万円以内であれば課税なし
-
相続時精算課税制度なら2,500万円まで非課税 →数年にわたる分割贈与や、相続時精算課税制度の利用など
を組み合わせることで、税負担を抑えることが可能です。
生前贈与・土地・評価額:まとめとアドバイス
-
評価額は「固定資産税評価額」「相続税評価額(路線価)」「実勢価格」の3種類がある
-
名義変更には贈与税・登録免許税・登記費用などがかかる
-
相続の方が節税効果が高い場合も多く、早期判断が重要
損をしないためには、評価額の確認と、税務・法務の専門家への相談が欠かせません。
生前贈与の手続きを検討している方は、専門家と一緒に進めることで、家族の将来を守る資産継承が実現できます。
生前贈与シリーズ|不動産と贈与の実務ポイント
関連記事リンク
👉 生前贈与・土地・名義変更:親が元気なうちに準備するスムーズな財産移転の方法
🏠 土地贈与の名義変更をスムーズに行い、贈与計画全体を滞りなく進めましょう。
👉 生前贈与・不動産・登記:名義変更と税金を正しく理解して後悔しない贈与にしよう
🏠 名義変更に伴う税金や手続きの基本を押さえ、贈与計画の精度を高めましょう。
👉 生前贈与・不動産・費用:かかるお金と節税の知恵を徹底解説
🏠 贈与に伴う費用全体を見通しながら、節税策を取り入れた計画を立てましょう。
外部リンク:国税庁|👉 贈与税(暦年課税)
関連記事リンク

さゆり:
相続のことって、つい後回しにしがちだけど、もめごとや損失を防ぐには「準備」が一番大事!
宇都宮で不動産を持っているなら、うちの特集シリーズで要点チェックしとくといいですよ~。
この下(👇)が、わたしが読みやすくまとめた、ぜんぶ実践的な内容ばかりですよ!
“争続”を避けるために必要な基礎知識と心構えを紹介。 📘 相続対策Ⅰ:非課税世帯でももめる?争族対策と遺言のすすめ
相続税がかからない家庭ほど、遺言の重要性が高まります。 📘 相続対策Ⅱ:資産があるなら必見!節税対策としての不動産活用術
評価減や特例の活用で、節税につながる不動産戦略を解説。 📘 相続対策Ⅲ:不動産オーナー向け|法人化・M&Aで資産を育てる相続へ
事業承継や法人化による長期的な資産管理の実例も紹介。 📘 相続対策Ⅳ:成功のカギは手順にあり|失敗しない相続の進め方
名義変更・登記・相続登記義務化までの実践ガイド。 📘 相続対策Ⅴ:認知症・信託・納税資金の備えで家族を守る
判断能力低下に備えた信託・成年後見・保険の活用法。 📘 相続対策Ⅵ:間違った節税で損しないために|出口戦略の考え方
節税だけでなく「将来売却時」を見据えた資産設計へ。 📘 相続対策Ⅶ:まとめ|7ステップでわかる“争わない・損しない”相続の実践法
プロローグ~第Ⅵ章を総まとめ!すぐ実践できる最終章。
🟧 売却相談(価格査定、相続物件の処分など):👉 不動産の売却
🟧 購入相談(資金計画、住宅ローンなど):👉 不動産の購入
🟧 境界線や共有名義の問題:👉 不動産の共有名義 |
👉 遺産分割 |
👉 境界・接道・トラブル
🟧 空き家・老朽化した建物の活用・管理:👉 空き家・空き地管理 |
👉 リフォーム・活用案
👉 相続不動産の手続き・税金を整理した「相続のまとめページ」はこちら
by エステート丙(ひのえ) since 2014