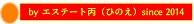生前贈与・マンション・売却:贈与と売却の税金・手続きの違いを徹底解説
「親からマンションを生前贈与してもらったけど、その後どうすればいいの?」「売却時にかかる税金は?シミュ
レーションしておきたい」
この記事では、「生前贈与・マンション・売却」をテーマに、贈与された不動産の税金や、売却時の注意点、贈与
と相続の違いなどを解説します。これからのマンション売却を検討されている方へ、安心して判断できる知識をご
提供します。

| ・生前贈与・マンション・売却:親から贈与された場合にまず確認したいこと ・マンション贈与の基本:親子間で名義変更したら? ・贈与されたマンションを売却すると税金はどうなる? ・生前贈与・マンション・売却:贈与税のシミュレーションと節税ポイント ・マンションを贈与されたら贈与税はいくら? ・1000万円贈与したら?非課税にできる? ・贈与税を払えない!そのときは? ・生前贈与・マンション・売却:売却時の税金と計算方法を理解する ・贈与を受けた不動産を売却する場合の税金の仕組み ・生前贈与と相続後の売却、どちらが得? ・関連記事リンク ・生前贈与・マンション・売却:贈与と売却をスムーズに進めるために |
生前贈与・マンション・売却:親から贈与された場合にまず確認したいこと
親子間でマンションの贈与が行われた場合、売却の際には通常の不動産売却とは異なる税務上のポイントがいくつ
か存在します。
マンション贈与の基本:親子間で名義変更したら?
親が元気なうちにマンションの名義を子に変更する「生前贈与」は、相続対策としてよく用いられます。ただし、
贈与には次のような注意点があります:
-
贈与税が課税される(年間110万円以上の価値の場合)
-
登録免許税や登記費用がかかる
-
固定資産税や管理費の名義変更も必要
名義を変える=費用がかかることを前提に、メリットとデメリットを整理しましょう。

贈与されたマンションを売却すると税金はどうなる?
贈与を受けたマンションを売却すると、「譲渡所得税」が発生します。ここで重要なのが取得費の引継ぎルールで
す。
-
贈与を受けた場合、原則として贈与者の取得費を引き継ぎます(親が買った金額)
-
長期保有(5年超)か短期保有(5年以下)によって税率が異なります
売却益が出た場合は、贈与税に加えて所得税も負担しなければならないため、ダブル課税のような状況になる可能
性があります。
生前贈与・マンション・売却:贈与税のシミュレーションと節税ポイント
贈与税は、「もらった金額」や「受贈者の状況」によって大きく変わります。
マンションを贈与されたら贈与税はいくら?
例:評価額3,000万円のマンションを子どもに贈与した場合
-
基礎控除:110万円
-
課税価格:2,890万円
-
税率:45%(控除額265万円)
→ 贈与税額:約1,035万円
このように、高額な贈与税が発生するため、事前に税理士によるシミュレーションが不可欠です。
1000万円贈与したら?非課税にできる?
-
暦年課税制度を使えば、毎年110万円まで非課税
-
分割贈与すれば数年かけて非課税で贈与できる可能性も
-
ただし、分割が「計画的贈与」と判断されると否認される場合も
贈与税を払えない!そのときは?
-
金融機関からの借り入れ(贈与税支払い用)
-
相続時精算課税制度の利用(2,500万円までは非課税)
-
不動産を売却して支払う方法(ただし納税猶予は不可)
いずれにせよ、贈与を受ける前に資金準備と税額試算をしておくことが重要です。
生前贈与・マンション・売却:売却時の税金と計算方法を理解する
贈与を受けた不動産を売却する場合の税金の仕組み
贈与を受けたマンションを売却すると、「譲渡所得」に対して所得税・住民税が課税されます。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却額 -(取得費 + 譲渡費用)
-
取得費は親が購入した価格を引き継ぐ
-
譲渡費用には仲介手数料や測量費用が含まれる
税率
-
長期譲渡(5年超):所得税15%+住民税5%
-
短期譲渡(5年以下):所得税30%+住民税9%
生前贈与と相続後の売却、どちらが得?
相続後にマンションを売却した場合、「取得費加算の特例」や「空き家3,000万円控除」など、税制優遇が多いた
め、相続後に売却した方が税金が少なくなる傾向があります。
ただし、相続が長引くと手続きが複雑になるため、ケースバイケースです。
生前贈与・マンション・売却:贈与と売却をスムーズに進めるために
マンションの生前贈与は、相続対策や家族間の財産移転に役立ちますが、税金や手続きの知識が不可欠です。
特に、売却を前提とする場合は贈与と売却の両方の税金を理解した上で、最適な方法を検討する必要があります。
まずは税理士や不動産業者などの専門家に相談し、納得のいく選択を目指しましょう。
生前贈与シリーズ|不動産と贈与の実務ポイント
関連記事リンク
👉 生前贈与・不動産・費用:かかるお金と節税の知恵を徹底解説
🏠 生前贈与にかかる具体的なコストや節税ポイントを理解し、贈与の損得判断に役立てましょう。
👉 不動産売却にかかる税金とは?初心者でもわかる節税と申告のポイント
🏠 売却時に発生する税金の仕組みを把握し、売却選択時の損得判断に役立てましょう。
👉 相続・不動産売却・税金対策:損をしないための節税ポイントと注意点
🏠 贈与後または売却後にかかる税負担を減らすための節税対策をあらかじめ捉えておきましょう。
外部リンク:国税庁|不動産の👉 贈与時の税金と👉 売却時の税金
関連記事リンク

さゆり:
相続のことって、つい後回しにしがちだけど、もめごとや損失を防ぐには「準備」が一番大事!
宇都宮で不動産を持っているなら、うちの特集シリーズで要点チェックしとくといいですよ~。
この下(👇)が、わたしが読みやすくまとめた、ぜんぶ実践的な内容ばかりですよ!
“争続”を避けるために必要な基礎知識と心構えを紹介。 📘 相続対策Ⅰ:非課税世帯でももめる?争族対策と遺言のすすめ
相続税がかからない家庭ほど、遺言の重要性が高まります。 📘 相続対策Ⅱ:資産があるなら必見!節税対策としての不動産活用術
評価減や特例の活用で、節税につながる不動産戦略を解説。 📘 相続対策Ⅲ:不動産オーナー向け|法人化・M&Aで資産を育てる相続へ
事業承継や法人化による長期的な資産管理の実例も紹介。 📘 相続対策Ⅳ:成功のカギは手順にあり|失敗しない相続の進め方
名義変更・登記・相続登記義務化までの実践ガイド。 📘 相続対策Ⅴ:認知症・信託・納税資金の備えで家族を守る
判断能力低下に備えた信託・成年後見・保険の活用法。 📘 相続対策Ⅵ:間違った節税で損しないために|出口戦略の考え方
節税だけでなく「将来売却時」を見据えた資産設計へ。 📘 相続対策Ⅶ:まとめ|7ステップでわかる“争わない・損しない”相続の実践法
プロローグ~第Ⅵ章を総まとめ!すぐ実践できる最終章。
🟧 売却相談(価格査定、相続物件の処分など):👉 不動産の売却
🟧 購入相談(資金計画、住宅ローンなど):👉 不動産の購入
🟧 境界線や共有名義の問題:👉 不動産の共有名義 |
👉 遺産分割 |
👉 境界・接道・トラブル
🟧 空き家・老朽化した建物の活用・管理:👉 空き家・空き地管理 |
👉 リフォーム・活用案
👉 相続不動産の手続き・税金を整理した「相続のまとめページ」はこちら
by エステート丙(ひのえ) since 2014