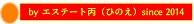生前贈与・不動産・費用:かかるお金と節税の知恵を徹底解説
「生前贈与で不動産を子どもに渡したいけど、費用や税金はどのくらいかかるの?」という疑問をお持ちの方は多
いのではないでしょうか。
この記事では、「生前贈与・不動産・費用」をテーマに、土地や家を贈与する際の税金・経費の内訳や、節税のた
めに知っておきたい制度をわかりやすく紹介します。将来的な相続との比較も交え、賢い選択ができるようご案内
します。

| ・生前贈与・不動産・費用:不動産贈与で実際にかかるお金とは? ・土地やマンションの贈与でかかる代表的な費用 ・非課税制度を使えば贈与税を抑えられる? ・生前贈与・不動産・費用:相続との比較と節税の考え方 ・生前贈与と相続、どちらが得か? ・不動産の贈与に経費はかかる? ・関連記事リンク ・生前贈与・不動産・費用:まとめと失敗しない進め方 |
生前贈与・不動産・費用:不動産贈与で実際にかかるお金とは?
不動産を生前贈与する際には、単なる登記費用だけでなく、多くのコストが発生します。中には見落としがちな税
金も含まれており、事前に把握しておくことが大切です。
土地やマンションの贈与でかかる代表的な費用
-
登録免許税:不動産の固定資産評価額の2%(贈与の場合)
-
司法書士報酬:登記代行を依頼する場合は5~10万円程度
-
贈与税:年間110万円を超える贈与は課税対象
-
不動産取得税:通常は発生しないが、自治体によって異なるケースも
-
契約書の印紙代や各種証明書取得費用
【参考例】
土地(評価額1,500万円)を親から子へ贈与:
-
登録免許税:約30万円
-
贈与税:課税額により数十万〜数百万円
-
司法書士費用や印紙代:約10万円
このように、贈与税を中心にまとまった支出が想定されます。
非課税制度を使えば贈与税を抑えられる?
以下の制度を使えば、生前贈与でも一定の税金を節約できます。
暦年課税制度とは?
毎年1人につき110万円までの贈与は非課税となる制度。
-
例:10年間で110万円×10年=合計1,100万円を非課税で贈与可能
-
不動産では現物贈与に工夫が必要(持ち分贈与など)
相続時精算課税制度とは?
-
2,500万円までは贈与税が非課税になる(ただし相続時に精算)
-
60歳以上の親から20歳以上の子・孫が対象
-
一度適用すると、以後すべての贈与が対象になるため注意
3000万円控除とは何か?
これは相続後に空き家を売却する場合の特例であり、生前贈与とは別制度です。
-
昭和56年5月31日以前の建物であることが条件
-
相続後に売却した際、譲渡所得から3,000万円まで控除できる
つまり、生前贈与で売却する場合には使えない制度です。生前贈与か、相続後の売却かで節税方法が異なる点に注
意しましょう。

生前贈与・不動産・費用:相続との比較と節税の考え方
生前贈与と相続、どちらが得か?
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 控除額 | 年間110万円 | 基礎控除:3,000万円+600万円×相続人 |
| 登録免許税 | 評価額の2% | 評価額の0.4% |
| 贈与税 | 累進税率10〜55% | 相続税も累進課税 |
| 節税制度 | 暦年課税・精算課税 | 小規模宅地・配偶者控除など |
結論としては、税負担だけを見ると相続の方が有利なケースが多いです。ただし、認知症などで判断能力が低下す
ると名義変更が難しくなるため、早めの対策が必要です。
不動産の贈与に経費はかかる?
不動産贈与は原則として譲渡ではないため「譲渡経費」の控除はありません。ただし、不動産の売却を前提とした
贈与・相続においては、売却時の譲渡所得計算で必要経費(取得費や仲介手数料など)は差し引くことができま
す。
生前贈与・不動産・費用:まとめと失敗しない進め方
不動産の生前贈与には、贈与税・登録免許税・司法書士費用など、さまざまな費用が発生します。一方で、節税制
度を上手に活用すれば、負担を抑えてスムーズに資産承継することも可能です。
まずは信頼できる税理士や不動産業者に相談し、自分のケースに合った最適な方法を選びましょう。無料相談を活
用して、安心の一歩を踏み出してください。
生前贈与シリーズ|不動産と贈与の実務ポイント
関連記事リンク
👉 生前贈与・不動産・登記:名義変更と税金を正しく理解して後悔しない贈与にしよう
🏠 費用だけでなく、名義変更や税金の基礎知識を併せて押さえましょう。贈与全体の理解が深まります。
👉 生前贈与・土地・名義変更:親が元気なうちに準備するスムーズな財産移転の方法
🏠 費用負担を意識しながら、実際にスムーズな名義変更へと進めましょう。
👉 生前贈与・建物登記:失敗しない手続きと費用のポイント
🏠 特に建物に関する贈与での細かな費用・手続きの注意点を知っておきましょう。
外部リンク:国税庁 👉 「暦年課税制度と相続時精算課税」
関連記事リンク

さゆり:
相続のことって、つい後回しにしがちだけど、もめごとや損失を防ぐには「準備」が一番大事!
宇都宮で不動産を持っているなら、うちの特集シリーズで要点チェックしとくといいですよ~。
この下(👇)が、わたしが読みやすくまとめた、ぜんぶ実践的な内容ばかりですよ!
“争続”を避けるために必要な基礎知識と心構えを紹介。 📘 相続対策Ⅰ:非課税世帯でももめる?争族対策と遺言のすすめ
相続税がかからない家庭ほど、遺言の重要性が高まります。 📘 相続対策Ⅱ:資産があるなら必見!節税対策としての不動産活用術
評価減や特例の活用で、節税につながる不動産戦略を解説。 📘 相続対策Ⅲ:不動産オーナー向け|法人化・M&Aで資産を育てる相続へ
事業承継や法人化による長期的な資産管理の実例も紹介。 📘 相続対策Ⅳ:成功のカギは手順にあり|失敗しない相続の進め方
名義変更・登記・相続登記義務化までの実践ガイド。 📘 相続対策Ⅴ:認知症・信託・納税資金の備えで家族を守る
判断能力低下に備えた信託・成年後見・保険の活用法。 📘 相続対策Ⅵ:間違った節税で損しないために|出口戦略の考え方
節税だけでなく「将来売却時」を見据えた資産設計へ。 📘 相続対策Ⅶ:まとめ|7ステップでわかる“争わない・損しない”相続の実践法
プロローグ~第Ⅵ章を総まとめ!すぐ実践できる最終章。
🟧 売却相談(価格査定、相続物件の処分など):👉 不動産の売却
🟧 購入相談(資金計画、住宅ローンなど):👉 不動産の購入
🟧 境界線や共有名義の問題:👉 不動産の共有名義 |
👉 遺産分割 |
👉 境界・接道・トラブル
🟧 空き家・老朽化した建物の活用・管理:👉 空き家・空き地管理 |
👉 リフォーム・活用案
👉 相続不動産の手続き・税金を整理した「相続のまとめページ」はこちら
by エステート丙(ひのえ) since 2014