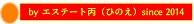生前贈与・建物登記:失敗しない手続きと費用のポイント
親から建物を贈与されたとき、必要になるのが「登記手続き」です。この記事では、生前贈与に伴う建物登記の流
れ、必要書類、費用、そして相続登記との違いまで、実務に役立つ情報を丁寧に解説していきます。安心して贈
与・登記を進めるためのヒントが満載です。

| ・生前贈与・建物登記:基礎知識と手続きの流れ ・手続き 司法書士費用 ・手続き 自分で ・生前贈与・建物登記:具体的な書類と申請方法 ・登記 必要書類 ・手続き どこで? ・申請書・流れ ・生前贈与・建物登記:名義変更と税務の注意点 ・不動産の名義変更の必要書類 ・名義変更 どうすれば? ・相続登記と贈与登記の違いは? ・ 確定申告は必要か? ・関連記事リンク ・生前贈与・建物登記:まとめとアドバイス |
生前贈与・建物登記:基礎知識と手続きの流れ
建物の生前贈与には、名義変更を伴う登記が必要です。登記は法務局への申請手続きで、不動産の所有権を第三者
にも明確にする重要な行為です。贈与による登記を放置すると、将来のトラブルや相続時の煩雑さの原因になるこ
ともあります。
手続き 司法書士費用
登記を司法書士に依頼する場合の費用は、報酬・登録免許税・必要書類の取得費用などを含めて10万~15万円程度
が一般的です。物件の評価額や地域によって変動するため、事前に複数の見積もりを取るのがおすすめです。信頼
できる司法書士に依頼することで、書類の不備やミスを防ぎ、スムーズな登記が可能になります。
手続き 自分で
登記は自分でも行えますが、手間とリスクがかかります。書類不備による補正指示や却下の可能性があるため、法
務局で相談しながら準備を進めましょう。申請書類の作成、登録免許税の納付、添付書類の準備など、慎重な確認
が必要です。
生前贈与・建物登記:具体的な書類と申請方法
登記 必要書類
-
贈与契約書
-
登記識別情報(権利証)
-
固定資産評価証明書
-
贈与者・受贈者の印鑑証明書・住民票
-
登記申請書 これらの書類を揃えたうえで、登記申請を行います。贈与契約書には贈与の内容や不動産の表
示、当事者の署名押印が必要です。
手続き どこで?
登記は「不動産の所在地を管轄する法務局」で行います。郵送でも申請可能ですが、初心者の場合は窓口に直接行
って相談しながら進める方が安心です。
申請書・流れ
申請書は法務局のホームページや窓口で入手できます。記入例に従って記入し、必要書類を添えて提出します。申
請から登記完了までは1~2週間程度が目安です。申請書の不備があると差し戻しになることもあるため、事前確認
を怠らないようにしましょう。
生前贈与・建物登記:名義変更と税務の注意点
不動産の名義変更の必要書類
建物の名義変更には、贈与者・受贈者双方の確認書類(印鑑証明、住民票など)と、登記申請書、贈与契約書など
が必要です。名義変更後には新しい登記識別情報(権利証)が発行されます。
名義変更 どうすれば?
-
贈与契約書を作成
-
評価証明書で登録免許税額を計算
-
登記申請書を作成
-
法務局に登記申請 という流れになります。
相続登記と贈与登記の違いは?
相続登記は登記義務化の対象となっており、3年以内の手続きが義務付けられています。一方、生前贈与による登記
は義務ではありませんが、名義を変更しないままだと不動産の売却や相続時に問題になるため、早めの登記が推奨
されます。(ただし、表示登記をしていない建物の贈与を受けた場合、基本的に表示登記は登記義務がありま
す。)

確定申告は必要か?
贈与を受けた年の翌年2月~3月に贈与税の申告が必要です。110万円を超える贈与には申告義務があります。贈与
税の申告を怠ると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、必ず期限内に対応しましょう。
生前贈与・建物登記:まとめとアドバイス
-
生前贈与による登記は、名義変更と贈与税の申告がセット
-
自分でも手続きできるが、司法書士の活用で安心感が増す
-
必要書類は多岐に渡り、早めの準備が肝心
将来のトラブルや手間を回避するためにも、贈与の意図が固まったら、早めに手続きを始めましょう。不動産の価
値や贈与の時期によって税額や手続きも変わるため、信頼できる専門家に相談することが、後悔しない贈与への第一歩です。
生前贈与シリーズ|不動産と贈与の実務ポイント
関連記事リンク
👉 生前贈与・不動産・登記:名義変更と税金を正しく理解して後悔しない贈与にしよう
🏠 建物だけでなく不動産全体の登記・税金知識を広く押さえ、トータルで手続きミスを防ぎましょう。
👉 生前贈与・不動産・費用:かかるお金と節税の知恵を徹底解説
🏠 登記手続きの費用負担を事前に把握し、節税を視野に入れた計画が立てましょう。
👉 生前贈与・土地・名義変更:親が元気なうちに準備するスムーズな財産移転の方法
🏠 土地と建物の登記手続きの違いを意識しながら、全体の財産移転をスムーズに進める知識がえられま
す。
外部リンク:国税庁|外部リンク:国税庁|👉 贈与税(暦年課税)
関連記事リンク

さゆり:
相続のことって、つい後回しにしがちだけど、もめごとや損失を防ぐには「準備」が一番大事!
宇都宮で不動産を持っているなら、うちの特集シリーズで要点チェックしとくといいですよ~。
この下(👇)が、わたしが読みやすくまとめた、ぜんぶ実践的な内容ばかりですよ!
“争続”を避けるために必要な基礎知識と心構えを紹介。 📘 相続対策Ⅰ:非課税世帯でももめる?争族対策と遺言のすすめ
相続税がかからない家庭ほど、遺言の重要性が高まります。 📘 相続対策Ⅱ:資産があるなら必見!節税対策としての不動産活用術
評価減や特例の活用で、節税につながる不動産戦略を解説。 📘 相続対策Ⅲ:不動産オーナー向け|法人化・M&Aで資産を育てる相続へ
事業承継や法人化による長期的な資産管理の実例も紹介。 📘 相続対策Ⅳ:成功のカギは手順にあり|失敗しない相続の進め方
名義変更・登記・相続登記義務化までの実践ガイド。 📘 相続対策Ⅴ:認知症・信託・納税資金の備えで家族を守る
判断能力低下に備えた信託・成年後見・保険の活用法。 📘 相続対策Ⅵ:間違った節税で損しないために|出口戦略の考え方
節税だけでなく「将来売却時」を見据えた資産設計へ。 📘 相続対策Ⅶ:まとめ|7ステップでわかる“争わない・損しない”相続の実践法
プロローグ~第Ⅵ章を総まとめ!すぐ実践できる最終章。
🟧 売却相談(価格査定、相続物件の処分など):👉 不動産の売却
🟧 購入相談(資金計画、住宅ローンなど):👉 不動産の購入
🟧 境界線や共有名義の問題:👉 不動産の共有名義 |
👉 遺産分割 |
👉 境界・接道・トラブル
🟧 空き家・老朽化した建物の活用・管理:👉 空き家・空き地管理 |
👉 リフォーム・活用案
👉 相続不動産の手続き・税金を整理した「相続のまとめページ」はこちら
by エステート丙(ひのえ) since 2014